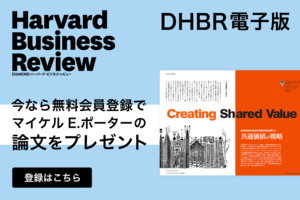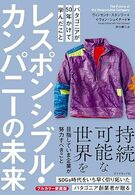アマビールとクレイマーは論文「進捗の法則」で、日々の小さな前進が社員の生産性を高めることを実証した。この小さな前進は、社会問題から個人の私生活にまで広く有効であることが多くの研究で明らかにされているという。
とても乗り越えられないような困難にぶつかったら、それを小さく分解するとよい。ミシガン大学の心理学者カール・ワイクの名著論文「小さな成功」によれば、大規模な社会問題は小さな単位に分解し、それぞれに達成可能な具体的目標を設定すべきであるという。たとえば失業問題のような大きな社会問題は、あまりに深刻なため解決不可能に見えるかもしれない。そのため、人は問題を避けて通ろうとするか、あるいは奏功するはずのない、ただ1つの壮大なる計画に行き着いてしまう。大きな問題を、小さいが最終的な目標へと続くステップに分解することで、恐れが減り、方向性が明らかとなる。そして早い段階で好ましい結果が生じる確率が上がり、それ以降の取り組みを助けることになる。
この「進捗の法則」――小さな成功の威力――は、企業の問題に対しても同じように当てはまる。筆者らが最近行った調査では、複雑な仕事に取り組んでいるチームや個人にとって、小さな成功を定期的に経験することの重要性が明らかとなった。真に重要な問題には、挫折が付きものである。どんなに小さな前進でも、またはその日の失敗から得た発見にすぎなくても、人は何らかの有意義な進捗を日々感じなければ、やる気を失ってしまう。小さな前進の追求は、長期的な目標の達成を促進する。スタンフォード大学教授のロバート・サットンは、名著Good Boss, Bad Boss(邦訳『マル上司、バツ上司』講談社)で次のように述べている。「社運を賭けた大胆な目標」(BHAG)は困難なだけでなく、往々にしてあまりにも単純で大ざっぱであるため、日常業務レベルで有効な指針に落とし込まれることがない。同様に、作家ピーター・シムズは著書Little Bets(邦訳『小さく賭けろ!』日経BP社)で、目標を段階的に設定することの重要性を力説している。