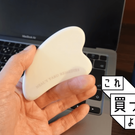紙とデジタルの使い分けは悩ましいですよね。でも、僕はもっぱらデジタル派。というとやや聞こえがいいかもしれませんが、単に悪筆な上に面倒くさがり屋で手帳や日記の類が続かないだけなんですけどね。
しかし、下手の横好きといいますか、文房具好きでもありますので手帳術の本にはついつい食指が伸びてしまいます。
本書も、美しい装丁と共にテーマがあのモレスキンということで注目していました。しかも共著者のお一人は、Lifehacking.jpを主宰し『できるポケット+ Evernote 活用編』や『iPhone情報整理術』の著書を持ちデジタルツールにも造詣の深い、堀正岳 氏。これは読まないわけにはいきません。
最新のITツールも華麗に使いこなしている著者は、モレスキンの手帳をどのように活用しているのでしょうか。
続きます。
さて、アナログ派デジタル派と言ってますが、著者はまずはその前提条件を見直す必要があると言ってます。つまり
「日々のことを記録するのにどのツールがいいのか」ではなく
「どこでどのツールを使えば、日々のことをすべて記録できるか?」
という前提に立つ必要があります。
1日の中にはどうしてもPCやiPhone・携帯電話などのIT機器を使えない場面もありますので、そういう場面では手帳の方に優位性があります。
また、それ以外にも紙の手帳が有利な場面として著者は
創造性の高い領域は、紙とペンとの方が有利であるとしています。確かに、自分の手を動かして、イラストなどを描いていると、PCで作業している時とは別の部分が刺激される感じがあります。一瞬のうちに浮かんだアイデアや考え、日々の記憶や思い出、ちょっとしたイラストやダイヤグラムなどといった、デジタルツールに収まりきらない創造性の高い領域です。
それでは、別にモレスキンではなくてもいいような気もしますが、モレスキンは他の手帳と比べて
- 堅牢性
- ボリューム
- 規格化
- DIY(改造・拡張の可能性)
の面で優位性があるとしています。
そして、本書の真骨頂と個人的に思っているのが、第三章、第四章で出てくる、モレスキン手帳を活用したGTDシステムの方法の部分でしょう。ITツール+モレスキン+GTDの見事な連携法をここまで見事に実行し文章化できるのはこの著者を置いていないでしょう。
後半部分は、モレスキンへの愛情があふれたさまざまなモレスキンの活用法が書かれています。
特に第7章の「モレスキンと相性の良い文房具」はヤバい。お値段もお手頃なものが多いので、買いまくってしまいそう。
毎年お布施のように「ほぼ日手帳」「超整理手帳」を買っていますが、僕も1冊モレスキンを入手したので、頑張って1冊使い切ってみよう。でも「ほぼ日手帳」って、すぐに買わないと売り切れちゃうんだよなあ。一応そっちも買っておこうかな。ついでに「超整理手帳」も。
(聖幸)